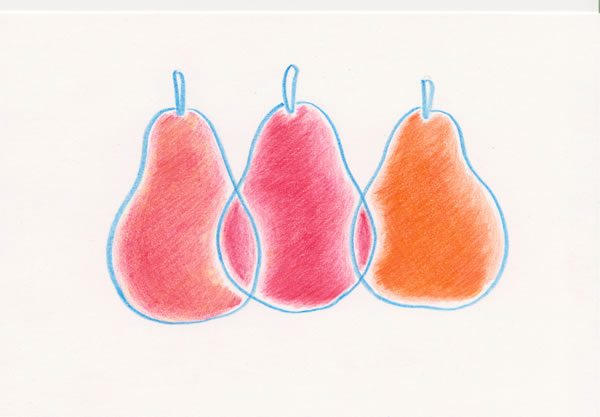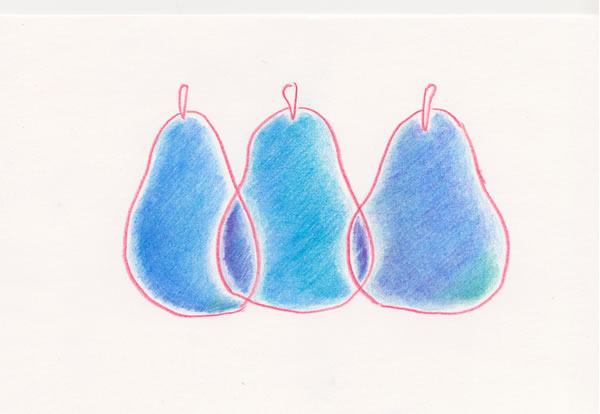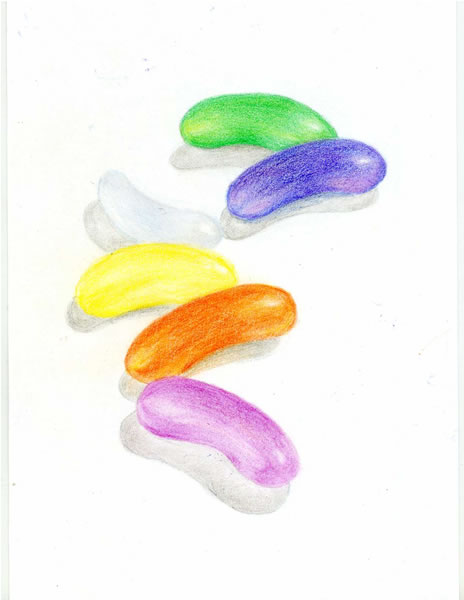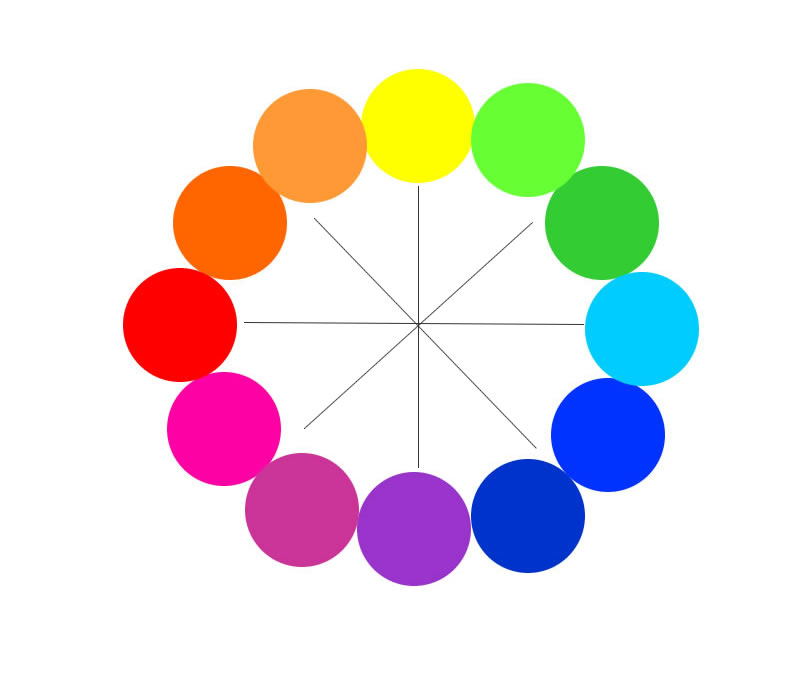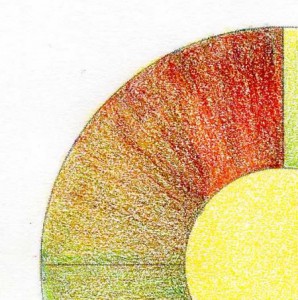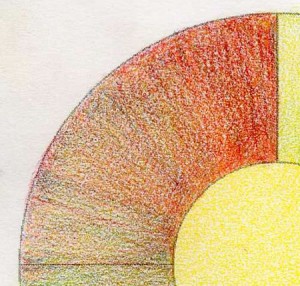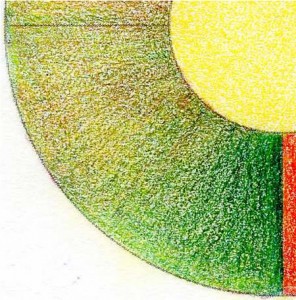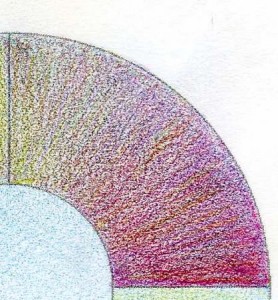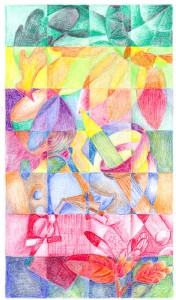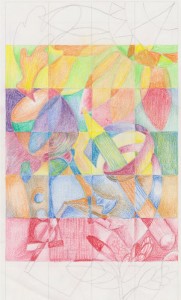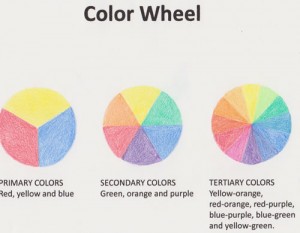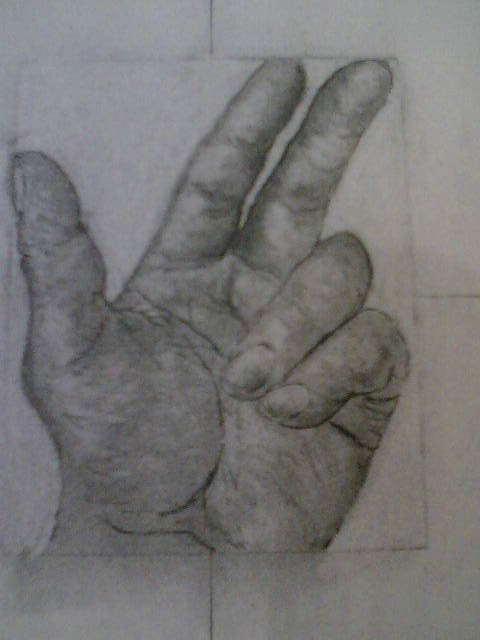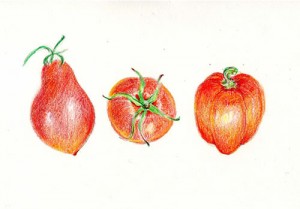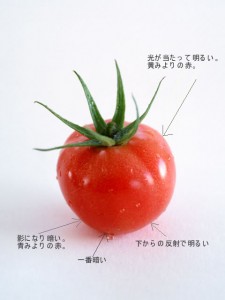塗り絵に活きる色彩学
塗り絵(色鉛筆画)を描くときにも、
色彩学の知識は大いに役立ちます。
例えば、ゼリービーンズを描くとき。
こういうのはどうでしょう?

グリーン一色だと、楽しそうな雰囲気は少ないですね。
では、こちらはいかがでしょうか?

赤は、目立つし、派手だし、元気いっぱいの色ですが、
そんなに楽しそうではないですね。
3枚そろうとにぎやかな感じがでますね。
この違いは、色相の数と差。
色相環の色がまんべんなく含まれていると、
カラフルで楽しい、お祭り気分の配色になります。
運動会の万国旗が良い例ですね。
ワクワク感が高まります。
反対に、色相の数が少ない、または色相差が少ないと、
例え赤でも、楽しいお祭り気分にはなりません。
強烈にはなりますが(笑)
塗り絵の際にも、
色彩の知識を活かすと、
表現の幅が広がりますね。
(in 大阪)
3Colors magic 3つの色から生まれる魔法 ②
やっと完成しました。
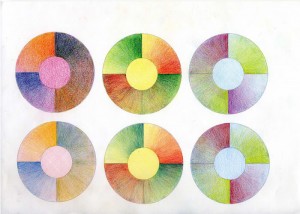
(クリックすると拡大し、鮮明になります)
上段も3色、
下段も3色のみ。
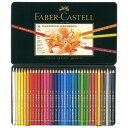
【送料無料・ラッピング無料】ファーバーカステル 色鉛筆 ポリクロモス色鉛筆 110036 36色… 価格:8,391円(税込、送料込) |
3Colors magic 3つの色から生まれる魔法
使った色鉛筆は3色のみ。
3色からいったいどれだけの色が生まれるのでしょう。
使った紙はPMパッド
色鉛筆は、ファーバーカステル ポリクロモス
Paper : Too pm Pad
colored pencil : Faber Castell polycromos
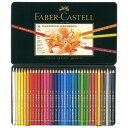
【送料無料・ラッピング無料】ファーバーカステル 色鉛筆 ポリクロモス色鉛筆 110036 36色… 価格:8,391円(税込、送料込) |
Lesson_02 混色レッスン_02
混色レッスン。
コンセプト、わかりますか?
下絵がフクザツすぎて、今一つでした。
次回は、下絵はシンプルにして再挑戦です。
このレッスン、限られた色で色を作ること、
色をよく見ること、
混ぜる分量や先に塗る色で、
色が大きく変化することなど、
とても勉強になりました。
分割数が多すぎて、雑多な印象になってしまいましたが。
最初の1枚でしたので、とにかく塗ってみよう!でした。
次の1枚は、どのモチーフを主役にするかを意識して、
配色を考えてみます。
塗りはじめる前に計画を立てること。
紙はPMバッド。
色鉛筆は、ファーバーカステル ポリクロモス。
マーカー用の紙ですが、インクジェットもキレイに発色します。
色鉛筆にも向いています。
薄くて透ける紙ですが、しっかりしていて使いやすい。
愛用の紙の一つ。
Paper : Too pm Pad
colored pencil : Faber Castell polycromos
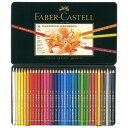
【送料無料・ラッピング無料】ファーバーカステル 色鉛筆 ポリクロモス色鉛筆 110036 36色… 価格:8,391円(税込、送料込) |
Lesson_01 混色レッスン_01
color wheel 色相環
カラーリストらしく、色相環を作りました。
色鉛筆は、ファーバーカステル ポリクロモス
colored pencil FaberCastell Polychromos
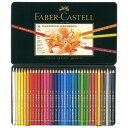
【送料無料・ラッピング無料】ファーバーカステル 色鉛筆 ポリクロモス色鉛筆 110036 36色… 価格:8,391円(税込、送料込) |
value Scale 明度 スケール
絵としては面白くないのですが、
スケーリングの練習です。
最低明度から最高明度まで。
一つの絵の中に、これが全て入っていると美しいと、
クリスティン・ニュートン先生から教わりました。
使用色鉛筆は、
Fabercastell のポリクロモス バーントアンバー。
紙は、
museのkmkケント200
セントラル画材オンラインショップ
ミューズ KMKケントブロック #200(厚口) A4 KL-5744

クリスティン・ニュートン先生の本
RBRの本
Hand graphite 手 鉛筆画です
今日の午後、松江から大阪へ移動です。
明日からオレンジ再開!
色鉛筆画でなくて、ごめんなさい。
3年前に描いた鉛筆画です。
鉛筆画を勉強する良い点は、
「明度」に対する感覚が養えること。
絵を描くとき、カラーの絵でも「明度」は大きな意味を持ちます。
明度を描くことで、立体感が表現できるのです。
参考文献
【大人の塗り絵】に役立つ色彩学 ナチュラルハーモニー
大人の塗り絵はアーティスティックがふさわしい。
アーティスティックな色鉛筆画への第一歩は、立体感。
プチトマトの塗り絵は、立体感の練習にぴったりなのです。
立体感を出すコツは、光と影。
ハイライトとシャドウを塗り分けると、
立体感がでてきます。
その際、役に立つのが色彩学の知識です。
自然界では光が当たっているところは黄色みを帯び、
影になっているところは青みを帯びます。
「ナチュラルハーモニー」ですね。
ルードがいう「色相の自然連鎖}
逆に言えば、ナチュラルハーモニーにすれば、
自然でなじみ深い調和となるわけです。
塗り絵をする場合も、
ナチュラルハーモニーを意識して色を付けると、
立体感を表現できます。
【大人の塗り絵】はアーティスティックに!ワークショップ (大阪)
はおかげさまで満席となりました。